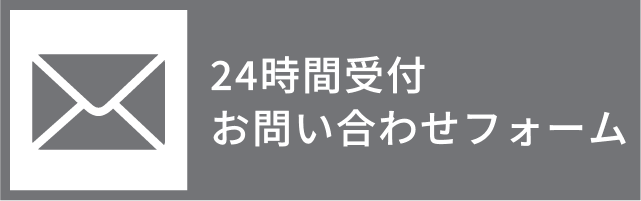Archive for the ‘相続税’ Category
【相続税】納税義務の変遷③
納税義務の変遷②の続きです。
在留資格などで日本で一時的に働いていた期間が10年を超えて本国に帰国すると、その者は非居住被相続人とはなりません。
この者について相続が発生すると、全世界財産について日本の相続税がかかってしまうという問題がありました。
平成30年度の税制改正で、非居住被相続人の範囲を拡大しました。
日本に10年超滞在して帰国した外国人の相続開始前10年以内において、国内に住所を有していた期間中継続して日本国籍なしであった者を非居住被相続人とすることによりこの問題に対処しました。
| 非居住被相続人 | 相続開始時において日本国内に住所がなかった被相続人であって次に掲げるものをいいます。 ①相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所があったもののうち、そのいずれの時においても日本国籍がなかったもの ②相続の開始前10年以内のいずれの時においても日本に住所がなかったもの |
贈与税の納税義務についても相続税と基本的には同じですが、非居住贈与者の範囲が異なります。
| 非居住贈与者 | 贈与の時において日本に住所がなかった者であつて次に掲げるものをいいます。 | |
| イ贈与前10年以内のいずれかの時において日本に住所があったものであつて次に掲げるもの | ||
| 日本国籍なし | (1)日本に住所を有しなくなつた日前15年以内において、住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの | |
| (2)日本に住所を有しなくなつた日前15年以内において、住所を有していた期間の合計が10年を超えるもののうち同日から2年を経過しているもの(※短期非居住贈与者) | ||
| ロ贈与前10年以内のいずれの時においても日本に住所を有していたことがないもの | ||
※短期非居住贈与者からの贈与については、一旦申告不要とされます。
・短期非居住贈与者が出国後2年以内に国内に住所を有することになった場合には、全世界財産が贈与税の課税の対象となります。
・短期非居住贈与者が出国後2年を経過した場合には、非居住贈与者になり日本国内の財産が贈与税の課税の対象となります。
現行の相続税・贈与税の納税義務については、極めて複雑な規定となっています。
財務省のホームページに表にまとめられたものがありますので参考にしてください。
(財務省HP 👈クリック)
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【相続税】納税義務の変遷②
納税義務の変遷①の続きです。
平成25年の税制改正後もいくつかの問題がありました。
①子供に外国籍を持たせ海外に居住させるとともに、親自身も海外に移住すれば、国外財産について相続税が課税されない。
②子供に日本国籍があっても、親子共々5年超海外に移住するすれば、国外財産について相続税が課税されない。
③在留資格などで日本で一時的に働いているにもかかわらず、日本に住所を有しているために、本国にある財産も日本の相続税の課税対象されてしまう。
平成29年の税制改正で、これらの問題ついてつぎのように対応しました。
①について
外国籍で海外に居住する子供であっても、親自身が相続開始前10年以内に日本に住所を有していれば、全世界財産について相続税を課税する。
②について
相続人又は被相続人のいずれかが相続開始前5年以内に日本に住所を有している場合は、全世界財産について相続税を課税するとしていましたが、この5年の期間を10年に伸ばしました。
③について(平成30年度の税制改正で一部変更されていますのでご注意ください。)
日本に住所を有する相続人が一時居住者であって、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合は、日本にある財産についてのみ相続税を課税する。
| 一時居住者 | 相続開始時に在留資格を有する者で相続開始前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの。 |
| 一時居住被相続人 | 相続開始時において在留資格を有し、かつ、日本国内に住所があった被相続人であって、相続開始時前15年以内において日本国内に住所をあった期間の合計が10年以下であるものをいいます。 |
| 非居住被相続人 | 相続開始時において日本国内に住所がなかった被相続人であって次に掲げる者をいいます。 ①相続開始時前10年以内の何れかの時において日本国内に住所があったことがあるもののうち相続開始時前15年以内において日本国内に住所があった期間の合計が10年以下のもの(この期間引き続き日本国籍を有していなかったものに限る。) ②相続開始時10年以内のいずれの時においても日本国内に住所がなかったもの。 |
在留資格などで日本で一時的に働いていた期間が10年を超えて本国に帰国すると、その者は非居住被相続人とはなりません。
この者について相続が発生すると、その相続人が日本に住所なし・日本国籍なしであっても、全世界財産について日本の相続税がかかってしまうことになります。
この点について、平成30年度の税制改正で、日本で一時的に働いていた外国人の出国後の一定の相続については、日本にある財産についてのみ相続税の課税をするとこととしました。
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【相続税】納税義務の変遷①
相続が発生した場合、亡くなった人が日本人で相続人も日本人というのであれば、全世界に所在する財産について相続税を納める義務があります。そうでないと不公平だからです。
では、外国人が日本に来て住んでいて相続が発生したら、納税義務はどうなるのでしょうか。
本来、相続税の納税義務については、次のとおり住所をキーとしたシンプルな作りでした。
・相続人が日本に住所を有していれば、日本の国内外を問わずすべての財産(全世界財産)に対して相続税を課税する。
・相続人が日本に住所を有していなければ、日本国内にある財産に対してのみ相続税を課税する。
しかし、これでは子供を海外に移住させれば、国外財産について相続税の課税を回避することができてしまいました。
平成12年の改正(租税特別措置法)で、次のいずれにも該当する場合は全世界財産に納税義務を課すことにしました。
・相続人が日本に住所を有していなくても日本国籍を有している。
・相続人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本に住所を有していた。
これでも、相続人が日本国籍でなければよいので、例えば子を米国で出生しそのまま居住させれば、国外財産について相続税の課税を回避することができてしまいました。
平成15年の税制改正で、上記規定は租税特別措置法から相続税法に取り込まれました。
平成25年の税制改正で、相続人が日本に住所も日本国籍も有していない場合であっても、被相続人が相続開始時に日本に住所を有していれば、全世界財産に納税義務があるとしました。
この改正でも、次の場合には国外財産について相続税の課税を回避することができました。
・子供に外国籍を持たせ海外に居住させるとともに、親自身も海外に移住する。
・子供に日本国籍があっても、親子共々5年超海外に移住する。
また、納税義務と課税財産の範囲は、日本における住所の有無で決まってしまうので、在留資格などで日本で一時的に働いている人たちにとっては問題がありました。
この人たちは、日本に住所を有しているために、日本にある財産のみならず、本国にある財産も日本の相続税の課税対象になってしまうからです。
これらの問題に対処するために、平成29年と30年に、相続税の納税義務について改正がされています。
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【相続税】仮想通貨と相続税
暗号化された仮想通貨の税務の取り扱いについては、令和元年の税制改正で整備されました。
また、国税庁より「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」が公開されています。(国税庁HP 👈クリック)
仮想通貨はインターネット上のデジタルな無記名の資産とされていますが、そもそもこれが相続財産となりうるのでしょうか。
◇相続財産についてい(国税庁HP 👈クリック)
『仮想通貨については、「決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されていることから、被相続人等から仮想通貨を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税される』としています。
◇ 評価方法について(国税庁HP 👈クリック)
・活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価する。
・活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、・・・、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価します
仮想通貨を相続した場合、留意すべき点があります。
仮想通貨には、通貨などの資産で担保されたステーブルコインという比較的値動きの小さい仮想通貨もあるようですが、ビットコインのような値動きの激しいものもあります。
仮想通貨の評価は、相続開始時の時価に対して課税されます。
いざ相続税を納付するとなった時点では大きく値下がりしてしまっているということも起こりえます。
また、その仮想通貨そのものを引き出せるのかという問題があります。
仮想通貨は、インターネット上のサービスを利用してIDとパスワードを決めて登録・保管する方法、被相続人のパソコンにソフトウエアをインストールして保管する方法、USBなどのデバイスに保管する方法、紙で秘密鍵などを保管する方法、があるようです。
被相続人が仮想通貨をどのように保管していたのかを調べる必要があります。
仮に保管方法が分かっても、IDやパスワードが分からなかったり、秘密鍵などを印刷した紙が見当たらなかったりすると、その仮想通貨は永遠に引き出すことができません。
それでは、仮想通貨を引き出すことができなかった場合、相続税の取り扱いがどうなるのでしょうか。
国税庁の方針としては相続財産として課税するということのようです。
これは、パスワードを知っているかどうかは相続人にしか分からないことなので、課税の公平の観点から課税庁としては相続税を課税するということだろうと思います。
何れにせよ、仮想通貨を保有したまま相続が発生すると、相続人は大変だと思います。
藤巻議員:仮想通貨の相続時の税制についてお聞きしたいんですが、仮想通貨のリスクというのは、パスワードを忘れちゃうともう引き出せないということがあるわけですね。(中略)それでも相続税は掛かるのかどうか。
藤井氏:仮想通貨に関連いたしますビジネスがまだ初期段階なんだと思います。そして、パスワードとの関係でございますが、一般論として申し上げますと、相続人が被相続人の設定したパスワードを知らない場合であっても相続人は被相続人の保有していた仮想通貨を承継することになりますので、その仮想通貨は相続税の課税対象となるという解釈でございます。
(日経XTECH 👈クリック)
(注)藤井氏:国税庁次長兼国税庁長官心得(当時)
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【相続税・贈与税・所得税】死亡保険金の課税関係
生命保険契約には、保険契約者、保険料負担者、被保険者、保険金受取人がいます。
被保険者が亡くなった場合、保険金受取人が保険請求をすることにより、生命保険会社から死亡保険金が支払われます。
この場合の死亡保険金は、保険契約に基づき保険金受取人が受け取るものでああるため、保険金受取人の固有の財産であって、相続財産にはあたらないとされています。
相続財産ではないので、受け取った死亡保険金は遺産分割の必要はなく、遺産分割協議書への記載も不要ということになります。
死亡保険金が相続財産ではないから相続税はかからないかというと、「みなし相続財産」として相続税の課税の対象になります(相続税法3①一)。
もし仮に死亡保険金に相続税がかからないとしたら、預貯金で相続財産として残した場合とで平仄が取れないことになってしまいます。
死亡保険金は、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人の組み合わせにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
| 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税 目 | |
| ① | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| ② | 夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
| ③ | 夫 | 妻 | 子供 | 贈与税 |
①は、夫が保険料を負担していたので、保険料が生命保険金に化体したイメージでしょうか、これを妻は夫から相続するので、相続税が課税されます。
②は、妻が自分で保険料を支払っていたので、受け取った生命保険金が支払った保険料を上回る場合には、その上回る部分に所得税が課税されます。
③は、②の妻が受け取れば所得税でしたが、保険料を負担していない子が生命保険金を受け取るので、妻から子への贈与となり、贈与税が課税されます。
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【相続税】生命保険契約に関する権利
相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。(国税庁HP👈クリック)
生命保険には、解約返戻金が支払われるものがあります。
①父が子供を被保険者として死亡保険を保険会社と契約し、保険料を父が負担したとします。
| 保険契約者 | 保険料負担者 | 被保険者 |
| 父 | 父 | 子供 |
保険契約者は、保険契約上の各種権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務)を有するとされています。
したがって、保険契約者である父が、この保険契約をもし中途で解約したとすると、解約返戻金は契約者である父に支払われます
つまり、税務的な言い方をすれば、父は解約返戻金を受け取る「生命保険契約に関する権利」を有していることになります。
このような状況で、父が死亡した場合には、解約返戻金相当額を受け取ることができる権利(「生命保険契約に関する権利」)が父の本来の相続財産となります。
②では上記①の場合で保険契約者が被保険者である子供であったらどうでしょう。
| 保険契約者 | 保険料負担者 | 被保険者 |
| 子供 | 父 | 子供 |
①の場合は相続税の課税があって、②の契約形態をとったら課税がないのではバランスを欠きます。
②の場合も保険料負担者である父から「生命保険契約に関する権利」を相続したとみなされる、みなし相続財産となり相続税の課税の対象となります。(相続税法3①三)
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【相続税・贈与税】非上場株式の納税猶予制度の適用ケース
平成30年度の税制改正で、非上場株式の納税猶予制度は10年間の特例措置として、その要件が緩和されました。
特例措置を適用したとしても、つぎの事業承継者がこの制度を利用しない限り、原則としてその時点で納税しなければらなりません。
納税猶予を継続するには、創業者からその子供、さらにその子供と数十年に渡ってこの制度を利用していくことになります。
この制度には、長期間に渡って特定事由に該当しないか管理し続けられるのか、また継続届出書を失念せずに提出し続けられるのかのか、といった問題があります。
これらの問題点があったといても適用を検討してもよいケースがいくつか考えられますが、そのうちの一つがつぎです。
非上場株式の納税猶予の特例を利用するのは、非上場会社の株価が高く、贈与税や相続税が多額になってしまう場合です。
非上場株式の評価方法には、類義業種比準方式と純資産価額方式(国税庁HP👈クリック)がありますが、会社の規模が大きなればなるほど、類似業種比準価額のウエイトが高くなり、業績の影響を受けやすくなります。
「売上そのものは好調なのだが、これから数期に渡って設備の大規模更新をするため減価償却費が多額となり赤字が見込まれる。」
こういった場合は、一時的に株価が低くなることが見込まれます。
非上場株式等の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた非上場株式は、贈与者である先代経営者が死亡した場合には、その特例の適用を受けた非上場株式等は、相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します(国税庁HP👈クリック)。
つまり、一時的に低いときの株価で将来相続税が計算できることになります。
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【相続税・贈与税】非上場株式の納税猶予制度のリスク
平成30年度の税制改正で、非上場株式の納税猶予制度は10年間の特例措置として、その要件が緩和されました。
・猶予の対象となる株式が3分の2から100%
・相続の場合の納税猶予が80%から100% 等々
ですが、中小企業庁がいう「爆発的に伸びている(中小企業庁HP👈クリック)」という実感はありません。
特例措置になって相続税・贈与税が100%納税猶予(一般措置:相続80%、贈与100%)となっても、つぎの事業承継者がこの制度を利用しない限り、原則としてその時点で納税をしなければらないことに変わりはありません。
納税猶予を継続しようとすると、創業者からその子供である事業承継者、さらにその子供(創業者からみれば孫)と数十年に渡ってこの制度を利用し続けることになります。
数十年先に社会が、そして会社がどうなっているか想像もつきません。そもそも孫が事業を承継してくれるかどうかわかりません。
非上場株式の納税猶予制度の適用を検討しても、いざ実行となると躊躇されるのは、こういった点にあるのかもしれません。
非上場株式の納税猶予制度のリスクで意外と見逃される点が、税務署への継続届出書です。
継続届出書は、経営承継期間内は毎年、その後は3年ごとに提出しなければなりません。
もし、継続届出書の提出を怠ると、猶予されている相続税・贈与税の全額と利子税を納付しなければなりません。
非上場株式の納税猶予制度は複雑ですが、一つひとつの手続きはさほど難しいものではありませんから、税理士などの専門家ならその実行は可能です。
しかし、長期間に渡ってこの制度を管理していくとなると納税者も税理士もある程度のリスクを伴います。
なぜなら、会社が資産管理会社に該当しないかなどの特定事由に該当しないか、猶予期間中ずっと見ていかなければならないからです。
また、継続届出書の提出が毎年ならまだよいのですが、5年経過後は3年に一度となると、うっかり提出の失念ということがあり得るからです。
さらに、会社の経理担当者が代わった、顧問税理士が代わった、顧問税理士事務所の担当者が代わったという場合、継続届出書の提出などの引き継ぎが漏れてしまうおそれもあります。
非上場株式の納税猶予制度は、少なくとも贈与時や相続時に非上場株式にかかる税金を用意しなくてもよい制度ですから、魅力的な制度です。
実行にあたっては、顧問税理士とよく相談して実行することが望まれます。
その意味で、非上場株式の納税猶予制度の実行だけを高い報酬で請け負う専門家は避けたほうがよいと思っています。
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【相続税・贈与税】非上場株式の納税猶予制度の趣旨
平成30年度の税制改正で、非上場株式の納税猶予制度は10年間の特例措置として、その要件が緩和されました。
・猶予の対象となる株式が3分の2から100%
・相続の場合の納税猶予が80%から100% 等々
これを受けて、所轄省庁である中小企業庁では下記のように評価しています。
・事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「法人向け事業承継税制」を、平成30年度の 税制改正で抜本的に拡充。
・ 拡充前は、年間400件程度の申請であったが、拡充後は足元の申請件数は年間6000件に迫る 勢いであり、爆発的に伸びている。(中小企業庁HP👈クリック)
制度が緩和されて申請件数は増えていると思いますが、爆発的に伸びているという実感はありません。6000件という数字は30年12月の1ヶ月分の申請件数を12倍したもので、やや誇張ぎみの感がします。
制度そのものは依然として複雑ですし、事業承継者は贈与税や相続税という租税債務を長期間に渡って背負っていかなければならない、要件を満たさければ一度に課税という、本質的な部分は変わっていないからだと思います。
この制度は事業承継税制と位置付けられているにも関わらず、不動産や金融資産の塊のような会社(資産管理会社)は除外されています。また、贈与時や相続時の雇用の平均がやむ得ない場合を除いて8割維持しなければならないなどの要件が付されています。
これは、制度創設の趣旨が中小企業で働く従業員の雇用の確保だからです。
中小企業オーナーの相続税対策を前面に出してしまうと、金持ち優遇と言われてしまうからだと思います。
本当に中小企業の株式が次世代への事業承継のネックとなっているのなら、一定の要件に該当する中小企業は、(例えば)20年会社が存続したら、猶予されていた相続税や贈与税は免除とすればよいと思います。中小企業オーナの目の色が変わり、もっと申請件数が増えると思います。
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【所得税・相続税】老人ホームへの入居と特例適用
住宅の取得、譲渡、保有、相続については、様々な税務上有利な特例があります。
・住宅借入金等特別控除(ローン控除)
・マイホームを売ったときの3,000万円の特別控特例
・マイホームを譲渡した場合の軽減税率の特例
・特定のマイホームを買い換えたときの特例
・マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・小規模居住用宅地等の特例
・その他、不動産取得税、固定資産税、登録免許税 等々
住宅について税金を優遇するのは、仮に住宅を売って利益が出たからといってストレートに課税してしまうと、つぎに住む住宅が買えなくなってしまいます。相続が発生したからといって相続税をまるまるかけてしまうと相続人の住む家がなくなってしまいます。
この他住宅関連産業は裾野が広いことから、景気対策として税制が利用されて来た面もあります。
このような住宅にかかる税務上の特例は、原則として住宅に実際に住んでいることが条件です。例外的にやむを得ない理由により、実際に住んでいなくても特例が受けられる場合があります。
例えば、住宅借入金等特別控除(ローン控除)は転勤等で住宅に住めなくなった場合であっても、家族が引き続き住んでいればローン控除が受けられます。
また、被相続人の居住用財産を売ったときの特例や小規模居住用宅地等の特例では、介護等が必要になったため老人ホーム等に入居した場合であっても、特例の適用が可能となっています。
ところで、被相続人の居住用財産を売ったときの特例と小規模居住用宅地等の特例老人ホーム等への入居の場合では、両者は微妙に取り扱いがことなるので注意が必要です。
-被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例-
自宅から老人ホーム等に移るときには要介護等の認定をうけていなければなりません。
| 被相続人が、・・・要介護認定若しくは要支援認定又は・・・障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、被相続人がその認定を受けていたかにより判定します。国税庁HP(👈クリック) |
-小規模居住用宅地等の特例-
必ずしも自宅から老人ホーム等に移るときには要介護等の認定を受けている必要はなく、相続時に要介護等の認定を受けていれば適用があります。
| 「被相続人の居住の用」には、被相続人の居住の用に供されていた宅地等が、養護老人ホームへの入所など被相続人が居住の用に供することができない一定の事由(次の(1)又は(2)の事由に限ります。)により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(省略)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前の被相続人の居住の用を含みます。国税庁HP(👈クリック)
(1) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。 |
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。